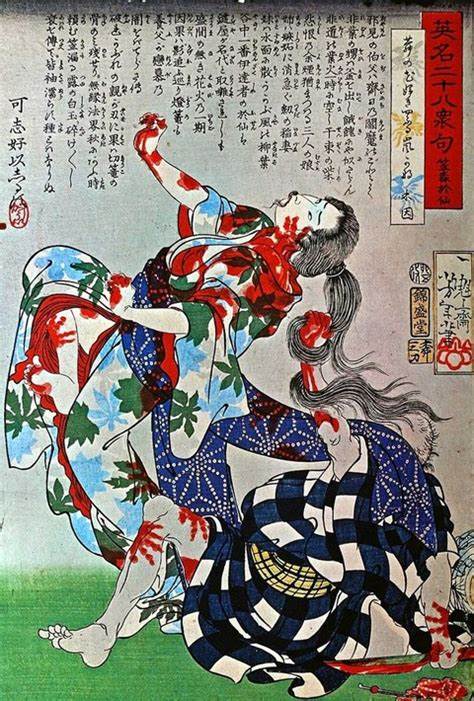月岡芳年
・・・最後の浮世絵師

コロナ禍で控えていた美術館巡り。
久しぶりに原宿の太田記念美術館に行った(9月11日)。
月岡芳年の浮世絵展、「血と妖艶」を観る。
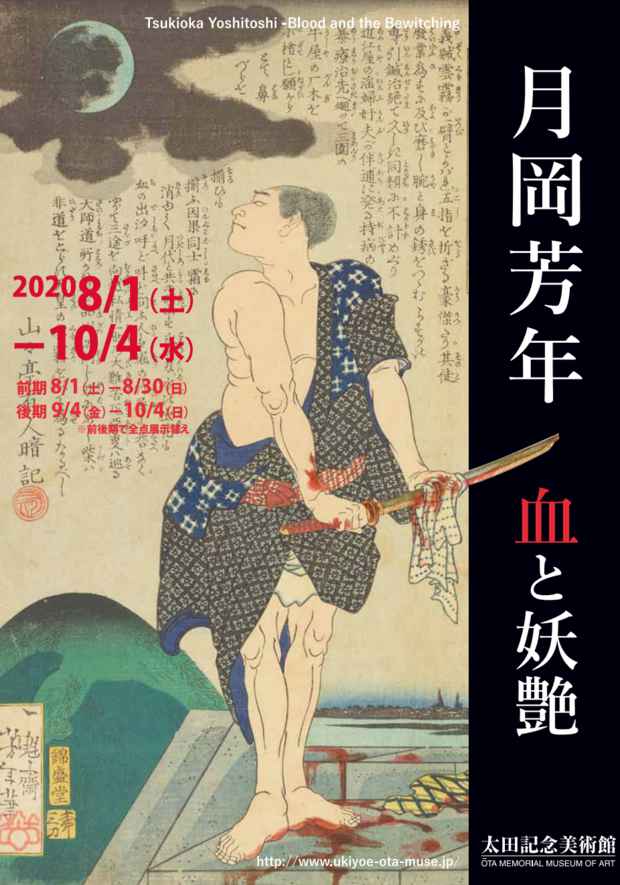
上、美術館ポスター。義賊雲霧仁左衛門の子分、因果小僧六之助。
正体がばれてやむなく殺した。「英名二十八衆句」から。
原宿は1年ぶり、あの時は<ロリータ・ファッション>の若い女の子たちがたくさんいて、
その姿を堪能した(おばさん風もいたが)。
コロナ禍の中でも、人通りも多く原宿は賑わっていって、やはり若者たちの町の雰囲気。
私が月岡芳年を<最後の浮世絵師>と呼ぶのは、
天保10年~明治25年(53歳没)と、江戸を生きた著名な絵師だから。
また、歌川国芳の弟子でもあり、国芳の影響もあった。
月岡芳年が浮世絵の題材としたジャンルは多彩で、作品数は1万点にも及ぶという。
中でも、<血みどろ絵>または<無惨絵>と呼ばれる分野が、月岡芳年の<特異なそれ>で、
江戸川乱歩や三島由紀夫を惹きつけたという。
美術館の紹介文によると、
<妖艶な美女と深い闇>
「月岡芳年の美人画には、単に外見が美しいだけではなく、
どことなく妖しさが漂う女性たちが数多く登場します。
また、闇を舞台にした作品には、張り詰めたような緊迫感や、
妖怪や幽霊たちの不気味な存在感があふれています。
美人画の代表作「風俗三十二相」や、
月にまつわる歴史や物語を描いた「月百姿」、
あるいは妖怪を題材とした「和漢百物語」や「新形三十六怪撰」など、
さまざまな作品を通して芳年の妖しい魅力を紹介します。」
<凄惨な血みどろ絵>
「月岡芳年は、残酷な殺戮シーンや死骸を描いた「血みどろ絵(無惨絵)」と通称されるジャンルを手がけました。
飛び散る血をセンセーショナルに描いたそのおどろおどろしい表現は、
江戸川乱歩や三島由紀夫など、大正・昭和に活躍した文学者たちを惹きつけたことでも知られています。
血みどろ絵の代表作「英名二十八衆句」全14点のほか、
「東錦浮世稿談」や「魁題百撰相」など、
芳年が描いた残酷な作品をまとめて紹介します。」と。
他方、美術館のカタログでは、
第1章「妖艶」、第2章「闇」、第3章「血」と章立てしている。
第1章では美人画の「風俗三十二相」。
美人画といえ、哥麿の典型的な姿と違って、
しなやかな肢体により色気を醸し出すような、くだけた絵姿を描く。
例えば
ねむさう :明治の娼妓の風俗。客が帰った後か、指や腕の<たおやかさ>にも色気がある。
あつさう :お灸をしている。文政の内室の風俗。
首から背中にかけて、むき出された<白い肌のうねり>が色っぽい。
いたさう :寛政の女郎の風俗。手ぬぐいを噛み締めて激痛に耐える。
馴染み客の名を腕に彫っている。<起請彫>というようだ。
さらに、芳年が生きた時代の風俗。
例
にあいさう :弘化の廓の芸者風俗。男装の麗人(吉原の芸者)。
手にした扇子に「俄」とあるのは、吉原の夏イベント、即興で芝居などをする。
出演者は男装(歌舞伎役者のように)したという。
遊歩がしたさう :明治の細君の風俗。洋装の一点。オシャレな帽子、ウエストのしまったドレス、洋傘。
明治を生きる若奥さまが美しく着飾ってお出かけ。ただ、日本髪は変わらない。
次いで、「月百姿」がある。月を背景に、様々な逸話を題材に描く。
例えば、「朝野河晴雪月 孝女ちか子」。構図が素晴らしい。
無実の罪で囚われた祖父のために、孫娘のちか子が身投げして無実を訴える。

また、「月のものくるひ 文ひろけ」。
狂女 :恋人の死を知らせる文を読み、狂った娘が手紙を身にまとい、徘徊する姿。
第2章「闇」、夜を舞台にした武者絵や歴史画など。
また、漆黒の闇の中でうごめく妖怪や幽霊たち。怪異に満ちた姿が描かれる。
下の「むさしのの月」は、満月の中一匹の寂しげなキツネが川辺にいる。
川面に映える自分の姿を見ているのだろうか。芳年は孤独な自分をキツネに託しているのか。

芳年は幕末から明治の動乱の時代を生きた。
彼は上野の彰義隊の敗残の姿をも写生したという。
「西郷隆盛霊幽冥奉書」は、死してなお政府に<もの申す>と建白する隆盛を。
西郷隆盛 :軍服姿もきめ細かく描いている。
「小笹原政尾の局」。「東錦浮世稿談」から。
蛇と女 :無数の蛇に絡みつかれた政尾の局。のぞく白い脚が色っぽい。
「卒都婆の月」。あの美の象徴、小野小町が老婆になってしまった。
小野小町
なお、芳年の傑作「奥州安達がはらひとつ家の図」も忘れずに。
残酷なので、政府により発禁処分とされた。
安達が原へのリンクあり。
また、産女(うぶめ)もあった。
以前、京極夏彦の小説と映画「姑獲鳥の夏」があった。ネタバレすると、想像妊娠だった。
産女とは妊婦が死んで幽霊となり、胎児をいとしむ姿のようだ。
「幽霊之図 うぶめ」
産女 :後ろ姿から赤ん坊の足が見える。
第3章「血」は、芳年の<血みどろ絵>の世界。
識者によると、芳年は血のりの感じを出すために絵の具に
膠(獣類の皮、骨、腸などを煮出した液を冷まして固めたもの)を使用している、という。
三島由紀夫は「英名二十八衆句」について、
「ここには、幕末動乱期を生き抜いてきた人間に投影した、苛烈な時代が物語られてゐる。・・・」と。
<血みどろ絵>は余りここに掲載したくないのだが。
とりあえず、
笠森於仙 見ての通り血なまぐさい絵。「英名二十八衆句」から。
フォトモーションのズームで文字を拡大できるようにした。
月岡芳年の画には、詞書あるいは書き入れが多くある。