ジャポニスム
私は奥行きや立体感を無視して平面を強調したクリムトの描き方、<黄金様式>に以前から興味を抱いていた。
都美術館「クリムト展」を観て、なを惹きつけられた。
しかも、その技法は日本美術、ことに<浮世絵>の影響があると知って、そこから<ジャポニスム>に至った。
日本では、幕末~明治維新~文明開化と欧米の科学・文化に追いつくことが求められ、浮世絵などは廃れてしまう。
黒船来航
逆に、欧米では万国博覧会(ウィーン万博1873)で日本の美術工芸品が出展され、エキゾティックな日本美術への関心が深まり、
<ジャポネズリー(日本趣味)>という造語さえ生まれた。
ウィーン万博日本館入口
日本館展示室
出品磁器 :染付花龍文の磁器
下、日傘を差すサラ・ベルナール

特に、画家たちにとって浮世絵とその描き方は、従来の写実主義と全く違う技法で、彼らに大きな影響を与えたようだ。
浮世絵は、色彩豊かな絵柄と地の部分との輪郭をはっきり分け、明瞭に絵柄を際立たせる。
これが板摺という版画の特徴を活かした描き方かもしれない。
①クリムトのジャポネズリー
クリムトの作品では、「愛」や「17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像」などに、
日本的(或いは東洋的)な装飾が施されている。
彼は日本美術に関する著書をかなり研究し、春画をも所持していた。
また、クリムトの主宰する1900年の第6回分離派展は日本美術を特集し、そのポスターは日本画になっている。
下、「愛」 :幸せそうな恋人たちの上にはなにやら不気味な群像。
これもクリムトらしい寓意か。
左右の花は当時流行のジャポニズムから
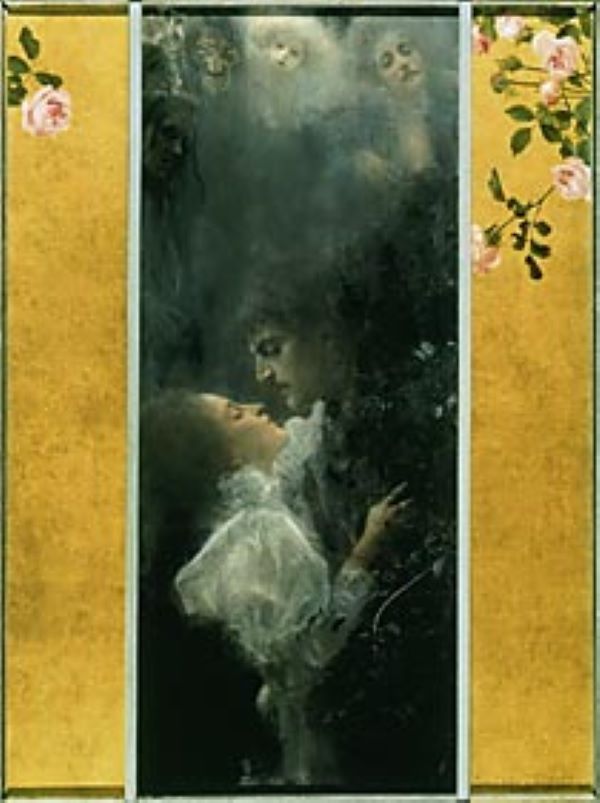
クリムトのページへのリンク
<ジャポネズリー(日本趣味)>はクリムトばかりでなく、ゴッホを初めとして多くの美術家、画家に及ぶ。
②ゴッホのジャポネズリー
ゴッホは、弟のテオと浮世絵をコレクションしていた(500点近いという)。
当時は、貧乏絵描きのゴッホでも手に入れられたほどだから、相当に廉価だったのだろう。
ゴッホ美術館(アムステルダム)に所蔵されている。
ゴッホ美術館ポスター
例えば、浮世絵を背景に描いた「タンギー爺さん」の肖像画は2点ある。
下の肖像画の背景には6つの浮世絵が描かれている。
*詳しくはゴッホのページに
下、「タンギー爺さん」 :ゴッホ作
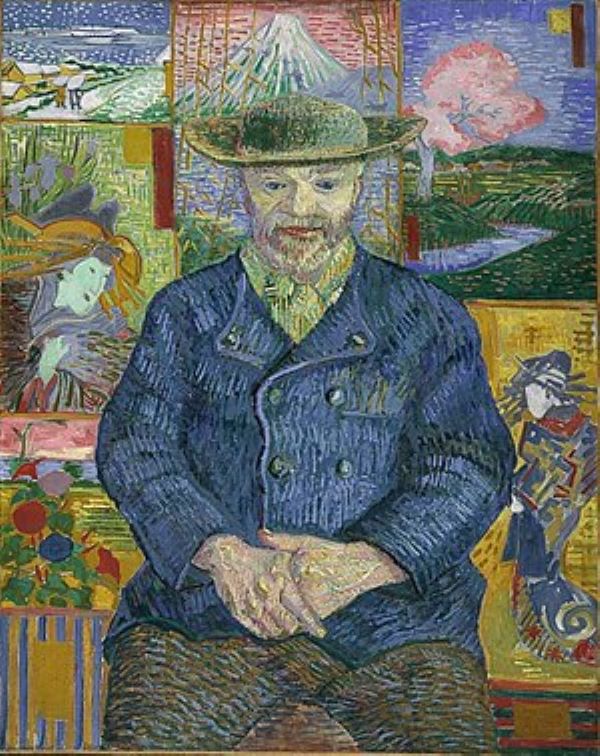
ゴッホのページへのリンク
③ジャポネズリーの画家たち
クリムト、ゴッホと紹介したので、ほか画家たちにも触れないといけないかなと。
浮世絵ばかりでなく、日本画の技法の影響がみられる。
彼らは、屏風や襖に描かれた花々、生け花などの日本風の独特の描写に興味をいだき、
また、色彩にあふれ豊かな装飾を施した日本の服装<和服>に魅了されたようだ。
クロード・モネ作、「ラ・ジャポネーズ」、モネ夫人カミーユがモデル。
私はこの作品がジャポネズリーの最高傑作と思う。
扇子の後ろのうちわ 利根川の舟 川口付近 銚子か。
人物以外の全てが日本風。茣蓙の上で立ち姿も芸者風、武者絵は誰かの作を模写したのかもしれない。
カミーユは32歳の若さで夭折、佳人薄命の典型。
下、「ラ・ジャポネーズ」 :モネ作

ジャポネズリの画家たち
「エミール・ゾラの肖像」 :エドァール・マネ
「磁器の国の姫君」 :ジェームズ・マクニール・ホイッスラー
「室内にいる日本の女」 :ユリウス・ヴィクトル・ベルガー
ジェームズ・ティソ作 屏風を眺める女性を描いてるが、この女性は何を見てるのだろうか?
「菊のある婦人像」 :エドガー・ドガ
「魔性のヴィーナス」 :ダンテ・ゲイブリエル
「オフェーリア」 :ジョン・エヴァレット・ミレイ
交響詩「海」の表紙。もちろん北斎ですね。 :クロード・ドビュッシー