浮世絵詞書
・・・下記の著者の読みごたえある著書を参考にした。感謝!
太田記念美術館で月岡芳年の「血と妖艶」展を観た時、
浮世絵に<詞書(ことばがき)>または<書き入れ>が多くあった。
それらの浮世絵の由来や物語を表すと思うが、悲しいかな読めない。
もちろん、展示では説明が付してあるが、後になると記憶が定かでない。
そこで、詞書について書かれた本はないかと捜したところ、
早川聞多著「現代語訳 春画」を見つけた。
著者は浮世絵の詞書とその現代語訳を掲載。
さらに、それらの説明や解説はとても丁寧で読みごたえある。
春画もいい。
詞書に何と書いてあるのか、江戸の町人と同じ目線で楽しめるかもしれない。
もともと春画は、江戸時代には<枕絵>とか<笑い絵>と呼ばれていた。
枕絵として、嫁入りする娘に親が持たせる例があったという。
笑い絵とは、男女の性器が顔と同じぐらいの大きさであったり、
あり得ないような体位で描かれたり、書入れには<洒落>があったりなど、
<笑いを誘う>絵も多かったからのようだ。
上記著書の内容は
杉村治兵衛作「欠題組物」
鈴木春信作「風流座敷八景」
磯田湖龍斎作「風流十二季の栄花」
喜多川歌麿作「ねがいの糸ぐち」
葛飾北斎作「富久寿楚宇」
<風流>とは<春画>のこと。
鈴木春信には「座敷八景」もあり、風流で春画を表している。
下は 杉村治兵衛作「欠題組物」の第二図。絵の上に長い詞書がある。
一応、フォトモーションのズームで拡大できるようにしたが。
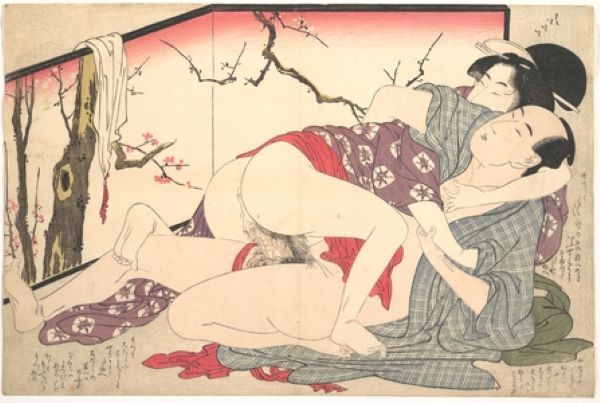
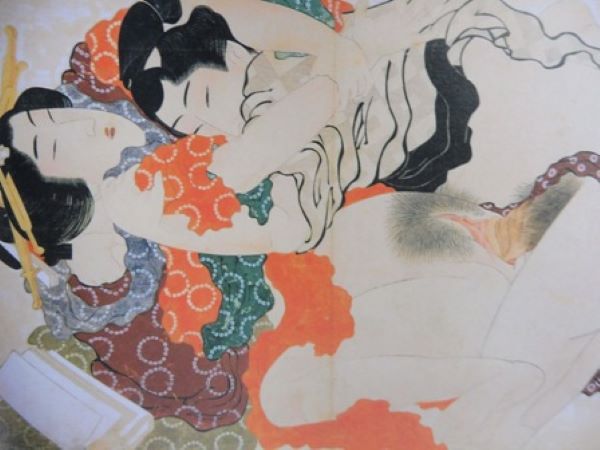
とりあえず、「富久寿楚宇」の八図と十図を観てみよう。
富久寿楚へのリンク